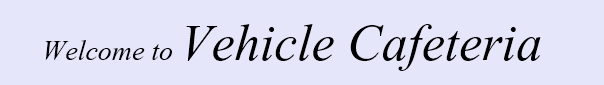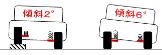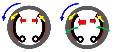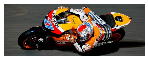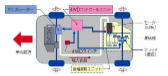ロジックで迫る雪道に強いクルマとは
Issued on Jan. 14, 2015
目次
5. 雪道走行での心構
5-1. 概要
雪道走行の装備が整った所で、ここでは雪道走行の心構えについてお伝えします。
一言で言えば、視界を確保して、とにかく滑らかな運転を心掛ける事です。
ついでに滑り止め用の砂の使い方も、ここでご紹介しておきたいと思います。
5-2. 急発進、急ブレーキ、急ハンドルを避ける
今時一般道でも急発進やら急ブレーキをする事もないでしょうから、次にいきましょう。
と言いたい所ですが、ちょっと待って下さい。
この良く言われる”雪道では急の付く運転を避ける”という標語は、一見正しい様に聞こえますが、はっきり言って間違いです。
これでは、急の付く運転さえしなければ雪道は大丈夫な様に聞こえますが、それでは全くもって不十分なのです。
正しくは、”雪道では一般道よりもっとゆっくり運転操作をしなければならない”です。
もっと言えば、雪道では一般道よりもっとゆっくりアクセルを踏んで、もっとゆっくりブレーキを踏んで、もっとゆっくりハンドルを回さなければいけないという事です。
すなわち、一般道と同じ様に発進したり、ブレーキを踏んだり、曲がったりしたら、雪道では滑って事故を起こす可能性があるというのを肝に銘じる必要があります。
5-3. スピードを控える
これも今更説明は不要でしょうが、とにかくスピードを控えれば、事故の確率はどんどん減っていきますし、万一滑ってぶつかったとしてしても被害は最小限で済みます。
とは言え、公道でいきなりスピードを落とすと、周りのクルマの迷惑になったり、視界不良の吹雪ですと却って追突される危険もあります。
ですので、ある程度周囲のクルマのスピードと歩調を合わせる事が必要です。
また視界の悪い雪道で、それも知らない道の場合、先頭を走るのはリスクが大きく、かつ非常に疲れる事です。

そこでお勧めなのが、もし旅先でしたら地元ナンバーの遅めのクルマの後に付いて走行する事です。
郷に入れば郷に従えは、何も世渡りだけに当てはまるものではありません。
また高速道路走行中でしたら、プロドライバーが運転する高速バスやトラックの後ろに、十分な車間距離を設けて付くのもお勧めです。

彼らはオンタイム走行と安全運行のプロですので、その後に付けて走ると、安全ですし単独走行と違い疲れ方が全く違います。
またバスやトラックの後ですと、轍も踏み固められており、多少走り易くなっています。
ただしディーゼルエンジン特有の排気ガスが車内入り込む可能性がありますので、外気レバーは閉にしておきましょう。
5-4. 車間距離を十分空ける
これもご存じでしょうが、車間距離は十分空けておきましょう。
できれば、いきなり前車が滑りだした場合に備えて、通常の2倍程度の車間距離は取っておきたいものです。
この場合、割り込まれても余裕で譲ってあげる寛容性が合わせて養われます。
5-5. 明りを早めに点灯する
雪の降る日の屋外は意外に明るいものの、走行中のクルマ同士は見難くなります。

そんなときは、早めにランプを点けて、自車位置を他車が容易に認識できる様にしましょう。
5-6. 視界を確保する
これもかなり大切な事です。
何方も経験があると思いますが、運転中に窓ガラスが急に曇って、気が付くと数センチの穴しか見えずにドキッとする事があります。
フロントガラスだけでなく、サイドウィンドウ、リアウィンドウが曇っても、間違いなく安全運転に支障をきたしますので、多少寒くても外気導入やエアコンをコマ目に調整する事をお勧めします。
また、急いで曇りを取りたい場合は、速やかに内気循環にしてエアコンをONする事です。
なお窓ガラスの内側が汚れていると曇り易いので、一度拭き掃除される事をお勧めします。
5-7. 滑り止めの砂は後ろに撒く
クルマが雪道の登り斜面で一旦止まってしまうと、再発進できない場合があります。
こんなときに助かるのが、路肩に設置されている滑り止めの砂です。
ところが、この砂を駆動輪の下に敷いたり、駆動輪の前に撒いたりしますが、これは間違いです。
滑り止めの砂は、駆動輪の後ろに撒きます。

滑り止めの砂は駆動輪の後ろに撒く
そして一旦クルマを後退させ、駆動輪を砂の上に乗せてからゆっくり前進するれば、動き(登り)出します。

上の写真の様に毛布やマットでも可能ですが、折角動き出した車両をまた止めて回収しなければいけない事を考えると、無料の砂が一番です。
そして次は雪道でのちょっとした運転テクニックについて、ご説明します。
5-8. 無視して構わないブースターケーブルの接続手順
この話もここに載せておきましょう。
ネットで検索すると、まるで言論統制でも敷かれているのではないかと思わせるほど画一的に、ブースターケーブルの接続手順が書かれています。
ちなみにその順番は以下の通りです。
①バッテリーが上がったクルマの⊕端子→②救援車の⊕端子→③救援車の⊖端子→④上がったクルマの⊖端子ではなくエンジンの金属部分
ですがこの順番は現実的には起こり得ないバッテリーの水素爆発を避けるために考えられた順番ですので、賢明な読者でしたら無視して頂いて全く構いません。
もし詳細についてお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
5. 雪道走行での心構/ロジックで迫る、雪道に強いクルマとは